教員採用試験の山場の一つである「集団面接」。
複数人の受験生と同時に評価されるこの形式は、個人面接とは異なる独特の難しさがあります。
「他の受験生に埋もれてしまわないか」
「自分の良さをどうアピールすればいいのか」
と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
以前集団討論のコツについて記述しましたが、集団面接にもまた、「コツ」が存在します!
この記事では、私が実際に集団面接を経験し、現役教員時代も多くの講師の先生と一緒に練習をする中で感じたコツを紹介していきます!
ポイント一覧
- 具体的な体験を解答の中に落とし込もう!
- 想定問題には必ず複数の回答を用意しておこう!
- 回答には一貫性を持とう!
- 個人面接とは違うということを忘れない!
*個人面接と集団討論についてはこちらの記事をご覧ください!
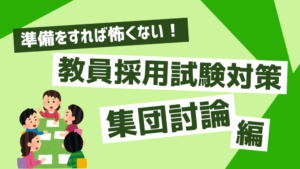
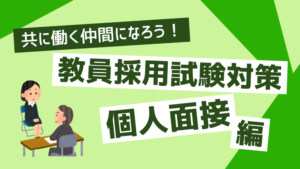
具体的な体験を回答の中に落とし込む
集団面接で最も大切なことの一つは、回答が「自分にしか語れないもの」であることです。
多くの受験生が同じような質問に対して、同じような模範解答を用意している中で、いかに個性を際立たせるか。その鍵は「具体的な体験」にあります。
体験談:8人中7人が「教科の専門性」をアピールした自己PR
私が教員採用試験を受けた時は8人での集団面接でした。
最初の1分間の自己PRの時間8人中7人が「教科の専門性」をアピールし、全員からもちろん熱意は感じました。
その中でも、たった一人だけ、鮮明に記憶に残っている方がいました。その方の自己PRがこちらです(記憶を頼りに書き起こしています!)。

私の強みは教科の専門性が高いことです。
私は前職で会社員として、日用品の開発に携わっていました。
その中で、科学がいかに私たちの身近な日用品に応用されているかを肌で感じてきました。例えば、シャンプーの泡立ち一つとっても、そこには界面活性剤の科学が深く関わっています。
社会人経験で知ったこのような科学と実生活のつながりを子どもたちに語り、科学が単なる教科書の中の知識ではなく、実社会と密接に結びついていることを伝えることで、子どもたちの興味や好奇心を育むことに貢献したいと考えています。
その方のPRは、他の受験生と同じ「教科の専門性」という結論でありながら、
『社会人経験での具体的な実感』
が加わることで、説得力と独自性を帯びていました。
一方で、私自身は当時「協調性」をアピールしました。
これもまた、多くの人がアピールしがちな強みなので、かぶっても良いように部活動での経験や具体的な数字を入れて自分独自のストーリーのあるPRにしていました。
当時の自己PR
私の強みは人と共にチームで働くための協調性です。
これまで中高大ともに部活動で人からの推薦で渉外部門でのリーダーを務めておりました。
吹奏楽の演奏会は部員のみだけでなく外部の方との調整・打ち合わせが必須となります。生徒同士だけでなく会館の方や地域の方とのコミュニケーションを大切にして様々な立場の人と1つの演奏会を作り上げる経験をしてきました。
大学生の時にはこの経験を活かして地域の方やお店と交渉をし、パンフレットに載せる広告件数を2年間で10件増加させることができました。
私は教育は個人で行うものではないと考えています。この協調性を活かして教員のみではなく保護者・地域の方の潤滑油となってチームで子ども達を支え成長できる場をつくることに貢献していきます。
書く文章でのポイントを知りたい方は以下からご確認ください!
自己PR解答例のポイント
私の強みは人と共にチームで働くための協調性です。
圧倒的結論ファースト!初めに結論を述べる。
〜〜生徒同士だけでなく会館の方や地域の方とのコミュニケーションを大切にして様々な立場の人と1つの演奏会を作り上げる経験をしてきました。
生徒間のコミュニケーションでは普通のコミュニケーション。それだけでない+α関わりを持っていたことをアピール!
〜〜パンフレットに載せる広告件数を2年間で10件増加させることができました。
1分間という短い時間の主張に説得力を持たせるには数字データがあるのがBEST!
私は教育は個人で行うものではないと考えています。
集団面接中に一貫して見せたい自分の教育観・姿勢をアピール
この協調性を活かして教員のみではなく保護者・地域の方の潤滑油となってチームで子ども達を支え成長できる場をつくることに貢献していきます。
強みを教育現場で「どのように」活かすつもりなのかを添えて終了する。
ただ強みをアピールするだけでは説得力は生まれません。
結論・主張が被っても「具体的」なら差別化できる
上記体験から学んだことは、結論や主張したいことが他の人と被ったとしても、いかに具体的で説得力があるかによって、印象が大きく変わるということです。
面接官は、「何を言ったか」だけでなく、「なぜそれを言ったのか」「どのような経験に基づいてその考えに至ったのか」を知りたいと思っています。
なぜならそういった原体験がないと机上の空論で一般論・理想論を語っているようにしか見えないからです。
イメージしやすいように以下に具体例を記載します。
例えば、「学校行事にはどのような意義があると思いますか?」という質問。どちらの方が説得力がありますか?
解答例1
学校行事の意義は友人の新たな一面を知ることができることだと考えいてます。
学校行事では係や役割が与えられるため普段とは違う人とコミュニケーションを取ることができます。
その中でそれまでとは違う一面を見ることができて、「こんな良さもあるのか」「この人にはこんな一面もあるのか」と感じ、絆を深めることができます。
このようにクラス単位での活動を通してクラスメイトの新たな一面に気付くことができるのが学校行事の意義だと考えています。
解答例2
私は最も大きな意義は、周囲の人間の新たな一面を知ることができることだと考えております。
私は高校時代、部活動に熱心だったためクラスの活動にあまり専念できていませんでした。
しかし学校行事の準備の中で、一人の友人と新たに話をする機会がありました。それまでただ寡黙な人という印象でしたが、演劇の脚本を制作する最中に読書家で多方面に知識が豊富であることを知りました。
そこからその友人とは今も連絡を取り合い困った時に協力をあおぐことがあります。
この友人の豊富な知識は学校行事がなければ知ることができませんでした。
このように授業を受けているだけでは知ることのできないクラスメイトの長所に気づく機会ができることが学校行事の意義だと私は思います。
分量の違いもありますが、後者の方が主張に説得力がありますよね?
実際の体験と、それが今の自分にもつながっていることを伝えると「この人は本気でそう思っていて、子どもたちにもそういう経験をさせてあげられるのではないか」と思ってもらえます。
主張の中に説得力を持たせるために、自分の具体例を入れ”一般論”からの差別化を図っていきましょう!
想定問題には複数の回答を用意しておく
集団面接では、他の受験生と回答が被ってしまうのは「つきもの」です。これは避けられないことですし、むしろ自然なことです。
回答の内容が被った時にどう対応するかで、面接官に与える印象は大きく変わります。
回答が被った時の焦りをなくすために複数の回答を用意しておくこと
もしあなたが、ある質問に対して1つしか回答を用意していない場合、他の受験生が先にその回答をしてしまったら、焦ってしまい、次の言葉が出てこなくなるかもしれません。
前の人とまったく同じ話をしてもダメです。そこで重要になるのが、想定される質問に対して、複数(最低でも2〜3つ)の回答を用意しておくことです。
この準備ができていると他の人と回答が被ってしまっても、「ああ、これはもう一人の自分が用意した回答を使おう」と冷静に対応することができます。
具体例:「授業がわからないと言われた時にどういう対応をしますか?」
例えば、面接で「授業がわからないと言われた時にどういう対応をしますか?」という質問が出たとしましょう。
回答例3パターン
- 回答1:自分の授業を振り返るための工夫
- 「まずは、自分自身の説明や進め方を振り返ります。授業の進め方や説明に問題がなかったか、客観的に振り返るために、授業を録画・録音して後で確認します。そして、どの部分で生徒が躓いているのかを具体的に分析し、改善策を練ります。」
- 回答2:生徒のつまづきを具体的に把握するための工夫
- 「生徒一人ひとりの理解度の把握に努めます。具体的には、授業後に振り返りカードや小テストを導入し、どこで、なぜつまづいているのか、具体的な感覚や疑問点を調査します。その上で、個別指導やグループワークを通じて、それぞれの生徒に合ったアプローチを作成していきます。」
- 回答3:興味・関心に焦点を当てた工夫
- 「生徒の好奇心を掻き立てる工夫をします。わからない以前に興味すらなく集中できていない可能性を加味し、教材研究をさらに深めます。生徒の興味を引くような導入や、日常生活と結びつけた具体的な題材、あるいは双方向的な進行ができるよう、授業の構成を再検討します。学ぶことの楽しさを伝えることで、自ら『分からない』を解消しようとする意欲を引き出したいと考えます。」
回答1〜3はどれも実際に現場に出たら並行して進めなければいけない作業になります。ただ、面接の場で理想の回答時間(30~60秒程度)で全て羅列すると内容の薄い一般論となってしまいます。



この工夫すべきポイントを細分化しましょう!
そうすることで具体的かつ複数の回答を用意できます。
面接官側からしても、回答が被るであろうことは想定済みです。
だからこそ、最後の方で他の人と被らない・具体性のある回答をすることができれば、柔軟性や視野の広さをアピールすることができます。
日頃から教育時事や教育法に対する意見を持つようにする
複数の回答を用意するためには、日頃から教育に関する書籍やニュースを読んで意見を持つようにしましょう!
以下におすすめ書籍を紹介しておきます!それぞれリンクになっています!
善は急げ!気になるものがあれば対策用に購入して勉強しましょう!



ただ読むだけで終わらせず「自分ならどうするのか」「何が大切だと感じたのか」意見を持つことを忘れずに!
教員採用試験速攻の教育時事 2026年度試験完全対応
実教教育出版 資格試験研究会 著
- 年度ごとに出版されているため最新情報を手に入れることができ
- 試験対策として販売されているため重要な考え方などもポイントを絞って知ることができる
- 筆記試験の対策にもなる
- テーマが複数あるため1冊から得られる情報が多い
フィンランド人はなぜ「学校教育」だけで英語が話せるのか
亜紀書房 米崎 里 著
- 教育大国フィンランドの教育について学べる本
- これまで受けてきた教育から一つ視野を広げることができる
- 何が違うのか、日本の教育の良さは?改善点は?と日本の教育について改めて考え直すことができる
ケーキの切れない非行少年たち
視聴新書 宮口 幸治 著
- ”できない”ことの背景は十人十色。何を考慮しないといけないのか知ることができる
- 合理的な配慮とは?インクルーシブ教育を実現するには?と言う問いへのヒントになるかもしれない
- 子どもたちの見えている世界の多様性を知ることができる
解答に一貫性を持つ
面接官は、回答の「内容」だけでなく、「人柄」や「教育観」を総合的に見ています。その中で、非常に重要になるのが「一貫性」および「信念」です。
回答全体から、「この人はこういうことを大切にしたいんだな」「こういう教師になりたいんだな」というメッセージが伝わるように意識しましょう。
ここからは
・一貫性がない回答の例
・一貫性を持たせるためにすべきこと
を書いていきます。
矛盾している回答の例:「傾聴力」と「わかりやすい説明」
面接を受ける上で、自分の大切にしたい教育観が一貫していることはとても重要です。
具体的な例を挙げましょう。
自己PRで「私の強みは『傾聴力』です。生徒一人ひとりの声に耳を傾け、その思いに寄り添うことを大切にしています」と力強く主張したとします。
その後の質問で「授業で最も大切にしたいことは何ですか?」と聞かれ、「生徒に内容が『わかりやすい説明』をすることです」と答えたらどうでしょうか?
どこに問題があるか感じ取れますか?一度立ち止まって考えてみてください!
日頃の会話の中であれば特に気にならないと思います。
しかし面接の場では以下のように捉えられる恐れがあります。
「話を聞くことが得意」とアピールしておきながら、
授業で大切にしたいことでは自分発信の「説明」に重点を置いている。
→面接官は「強みとして言っていることと、やろうとしていることにズレがあるな」という印象を与えてしまう。
これでは、あなたの主張に一貫性がなく、結果として「この人はどんな人だったかな?」という印象にも残ることができません。
ここで授業で最も大切にしたいこととして
「子どもたちが発言しやすい空気を作り意見交流が活発におこえるように工夫する」
と答えるとどうでしょうか?
面接後に「生徒の声を大切にしようとしていた子!」と思い出してもらえるかもしれません。
では、どうすれば一貫性を持つことができるのか、ここからはそこを解説します。
軸をぶらさないために自分の中の教育観を深掘りする
まずは解答を考える前に自分の教育観を深掘りしましょう!
以下に質問を10個かきます!自分の教育観を分析したい人はぜひ考えてみてください。
- あなたの座右の銘はなんですか?
- あなたはなぜ教員になりたいと思いましたか?
- 自分のクラスの生徒にはどんな人間になって欲しいですか?
- どんな雰囲気で毎日の授業を進めていきたいですか?
- 自分のクラスの生徒に絶対にしてほしくないことはなんですか?
- 周りの先生方とはどんな関わり方をしていきたいですか?
- 子どもたちに部活動を進めたいですか?理由とともに考えてください
- 自分の学生生活で一番強く印象に残っていることはなんですか?
- 教員になろうと思ったきっかけはなんですか?
- なぜその校種(・教科)の教員になろうと思いましたか?
ひとまずこれだけ回答すれば少しずつでも自分の大切にしたい芯の部分が見えてくるのではないかと思います。
面接の回答を作っていく段階でことあるごとに「自分が何を大切に教育をしたいのか」を考えるようにしましょう。
そして、面接全体を通して、どんな教師になりたいのか、何を大切にしたいのかという「一本の筋」が通るよう回答を構築しましょう。
集団面接という限られた時間の中で、「核」となる部分を面接官に伝えるためには、全ての回答がその「核」に繋がっているように見せることが重要です。
自分が大切にした教育観についてとことん深掘りし、理想の教育をしっかり伝えましょう!



きっとこの教育観の深掘りは教員になった後も自分を助けてくれます!
自己分析についてもう少し詳しく知りたい人はぜひこちらの記事も参考程度にご覧ください!
個人面接と違うということを忘れない!
集団面接は、あくまで「集団」での面接です。個人面接のように、自分が主役になって長く語り続ける場ではありません。
この違いを理解していないと、知らず知らずのうちに面接官に悪い印象を与えてしまう可能性があります。
以下にNGポイントと好印象を与えるためのポイントを書いておきます!
長すぎる回答、聞かない姿勢はNG
集団面接で最も避けたいのは、以下のような行動です。
- 解答が長すぎて他の人の回答を奪ってしまう
- 他の人の回答を聞いていない
「1つの回答には1つの主張」を徹底する
たくさん準備して臨む面接の場で、「考えたことを全て言いたい!アピールしないと」と思う気持ちはよく分かります。
しかし、一つの質問に対して長々と語りすぎると、他の受験生の回答の機会を奪ってしまいます。
あくまで1つの回答に1つの主張!という姿勢を維持しましょう。
面接官も受験生も未来の同僚!丁寧な傾聴の姿勢を保つ
自分の番が来るまでぼーっとしたり、他の受験生が話している間に次の自分の回答を考えたりしていませんか?
そもそも人が話している時に、興味なさそうにぼーっとして自分のことばっかり考えている人と「一緒に働きたい」とは思いませんよね。
協調性や傾聴の姿勢を示しこういう人と一緒に働きたい!と思ってもらうことが不可欠です。
協調性と配慮を示すことができているかの最終チェック!
集団面接は、「チームの一員」としてどれだけ貢献できるか、どれだけ周囲に配慮できるかを見られる場でもあります。
集団面接で、以下のような行動できているか今一度チェックしてみましょう!
- 穏やかな空気を作る
他の人が話しやすいように、笑顔で頷いたり、アイコンタクトを取ったりして、全体として良い空気を作るように心がけましょう。
こうすることで、その場の雰囲気を和ませることに繋がります。 - 「聞く姿勢」を見せる
他の受験生の回答中は、真剣に耳を傾け、共感を示すように頷きましょう。
これにより、「傾聴力」があるだけでなく、「他者を尊重できる人物」であるという印象を与えることができます。 - 簡潔に、しかし明確に
複数回答を用意していても、全てを語る必要はありません。
一つの質問に対しては、一つの結論を簡潔に、しかし力強く伝えることを意識しましょう。
*もし他の人と回答が被ってしまった場合は、「〇〇さんの意見に私も賛成です。加えて、私の経験から〜」のように、前者の意見を尊重しつつ、自分のオリジナリティを加える形で答えるのも効果的です。
まとめ
教員採用試験の集団面接は、確かに独特の緊張感があります。
しかし、今回紹介した「印象に残る工夫」を意識して準備し、本番に臨むことで、きっと面接官に強い印象を残すことができるはずです。
- 具体的な体験を解答の中に落とし込む
自分にしか語れないエピソードで、回答に深みと説得力を持たせる。 - 想定問題には複数解答を用意しておく
回答が被っても焦らず、冷静に対応できる引き出しを持つ。 - 解答に一貫性を持つ
あなたの教育観や人柄が、全ての回答からブレずに伝わるようにする。 - 個人面接と違うということを忘れない!
集団の一員としての振る舞いを意識し、協調性や配慮を示す。
これらのコツを実践し、自信を持ってあなたの魅力をアピールしてください!



熱意と個性が、面接官の心に響くことを願っています。応援しています!

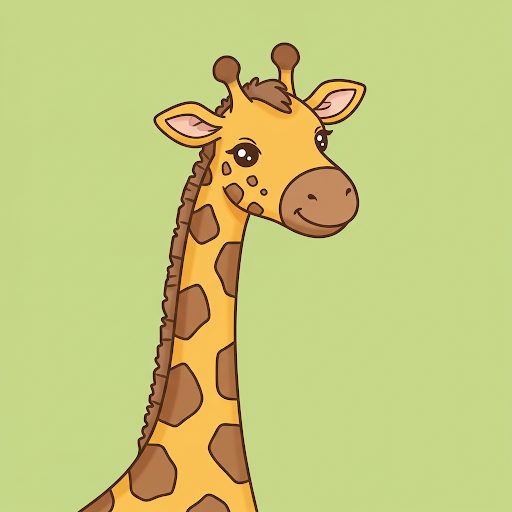
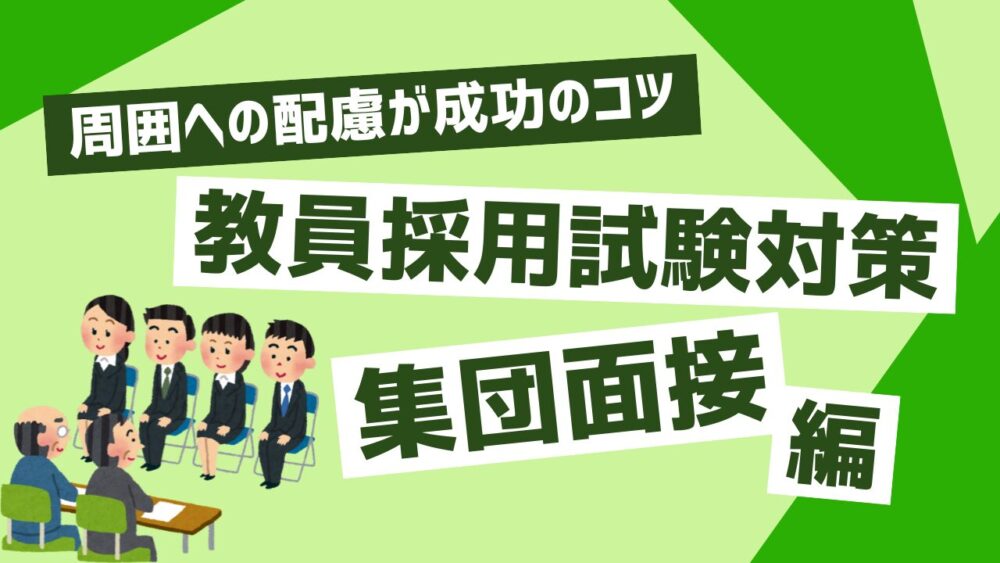




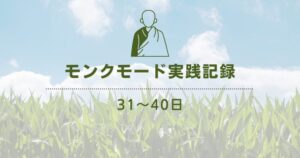

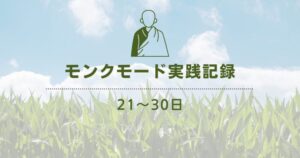
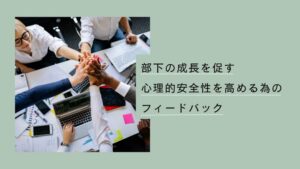
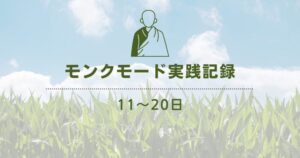
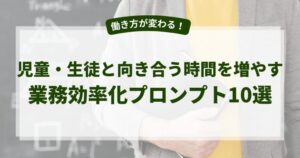
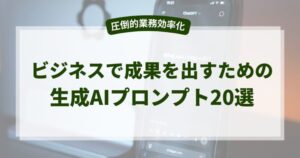
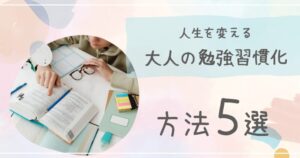
コメント