「1on1が気まずい沈黙で終わる」「良かれと思ったフィードバックが部下を萎縮させてしまう」
これらは多くのマネージャーが直面する悩みですが、その根本原因はスキル不足ではありません。
この記事はあなたのフィードバックを「指導」から「対話」へと転換します。具体的で実践的なガイドブックとしてご活用ください!
記事内容まとめ
- なぜ「心理的安全性」がフィードバックに不可欠なのか、その理由
- 具体的で強力なフレームワーク「SBIモデル」と、明日から使える「黄金フレーズ集」
- フィードバックを真の対話に変える「傾聴」と「問いかけ」のコツ
あなたの言葉でチームのパフォーマンスを最大化させましょう!
なぜ、あなたのフィードバックは響かないのか?根本原因は「心理的安全性」の欠如
効果的なフィードバックの技術を学ぶ前に、まず土台を理解する必要があります。「なぜ心理的安全性が重要なのか」を知ることが大切です。
心理的安全性とは?「ぬるま湯組織」との決定的な違い
「心理的安全性」とはそもそもなんなのか。
心理的安全性(psychological safety)とは、自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態のことです。ビジネスシーンにおいては、上司や同僚に異なる意見を言ったとしても、人間関係が破綻したり、相手から拒絶されたりしないと感じる状態を指します。
心理的安全性とは?ぬるま湯組織との違いや高める方法を解説 | NECソリューションイノベータ
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20230609_psychological-safety.html
この本質は「このチームでは対人関係のリスクをとっても大丈夫だ」と示すことです。メンバー全員が心からそう信じている状態を指します。
では、会社にける対人関係のリスクとは何でしょうか。
例えば
「無知だと思われるかも」
「無能だと思われたくない」
「これを報告すれば怒られるかもしれない」
という懸念です。
心理的安全性が確保された環境では、このような懸念から解放され、自分の意見や質問を率直に口にできます。あるいは失敗を話しても罰せられることはありません。
ここで決定的に重要なのは、心理的安全性の高いチームは決して「ぬるま湯組織」ではない点です。

この違いを、以前私が顧問をしていた部活動での体験談を通してお話しします。イメージが湧かない方は展開してみてください!
【体験談】私が顧問をしていた部活動での「ぬるま湯」からの脱却
私が顧問をしていたある部活動での話です。
先輩が後輩への指導をためらい、チームの規律が乱れていた時期がありました。
先輩から後輩への指導がうまくいかないうちに、徐々に後輩たちは練習に遅刻することが増えていきました。先輩へのリスペクトを欠いた言動をとることもありました。
この状況を見かねた私が部長と副部長に話を聞きました。「後輩に注意して、部活の雰囲気が悪くなるのが嫌だったんです」「自分たちが嫌われ役になりたくなくて…」と続けました。
この状態が「ぬるま湯組織」の状態です
表面的な仲の良さとは裏腹に、チームとしての基準は下がっていました。成長は完全に止まっていました。
このままでは良くないなとおもい部長と副部長にこう問いかけました。
「このままで、本当にみんなが成長できる良いチームになると思う?」
「先輩として、どういう部活動にしていきたい?」
この問いの後、部長と副部長は主体となって、部員全員での話し合いの場を設けました。
その話し合いでは、本音をぶつけ合ったそうです。そこで学年に関係なく「感情的に怒鳴られるのは嫌だ」という意見が出ました。
それは「なぜダメなのか理由を説明する」「人格否定はしない」といった内容です。
このルールには全員が納得していました。
▼規律と活気が両立するチームへ
このルールができてから2〜3ヶ月が経つと、部活動の規律は見違えるように改善されていきました。
しかし、後輩たちが一方的に黙るようになったわけではありません。むしろルールという共通の土台ができました。
例えば「この練習方法は、もっとこうしたらどうですか?」といった提案です。
これはチームが「ぬるま湯組織」から「心理的安全性の高い組織」へと生まれ変わった瞬間でした。
「チームをより良くする」という共通の目標ができ、その目標に向かって誰もが安心して発言できる信頼感が生まれたのです。
一見、部活動と会社組織とは違う世界に聞こえるかもしれません。しかしチームが成長していく上で直面する課題の本質は、驚くほど共通しています。
「チームの目標達成のために、誰もが安心してリスク(発言や指摘)を取れる状態」を意味します。
| ぬるま湯組織 | 心理的安全性の高い組織 | |
|---|---|---|
| 目的 | 対立を避け、仲良くいること | チームの目標を達成し、成長すること |
| 行動 | 問題を見て見ぬふりをする | 健全な対立を恐れず、指摘し合う |
| 結果 | 基準が下がり、成長が止まる | 基準が保たれ、チームも個人も成長する |
このような、率直な対話を恐れない文化は重要です。潜在的なリスクを早期に発見でき、そして革新的なアイデアを生むイノベーションに繋がります。
これがチームの持続的な成長の源泉となるのです。
発言を妨げる「4つの不安」
人が職場で発言をためらう背景には、4つの不安が存在すると言います。
あなたのフィードバックが、意図せずこれらの不安を刺激していませんか?
- 「無知だ」と思われる不安:
初歩的な質問ができず、理解のズレやミスに繋がる。 - 「無能だ」と思われる不安:
失敗の報告や助けを求めることをためらい、問題が深刻化する。 - 「邪魔だ」と思われる不安:
会議で意見を言えず、斬新なアイデアが埋もれてしまう。 - 「ネガティブだ」と思われる不安:
計画への懸念を口にできず、チームが間違った方向に進むのを止められない。
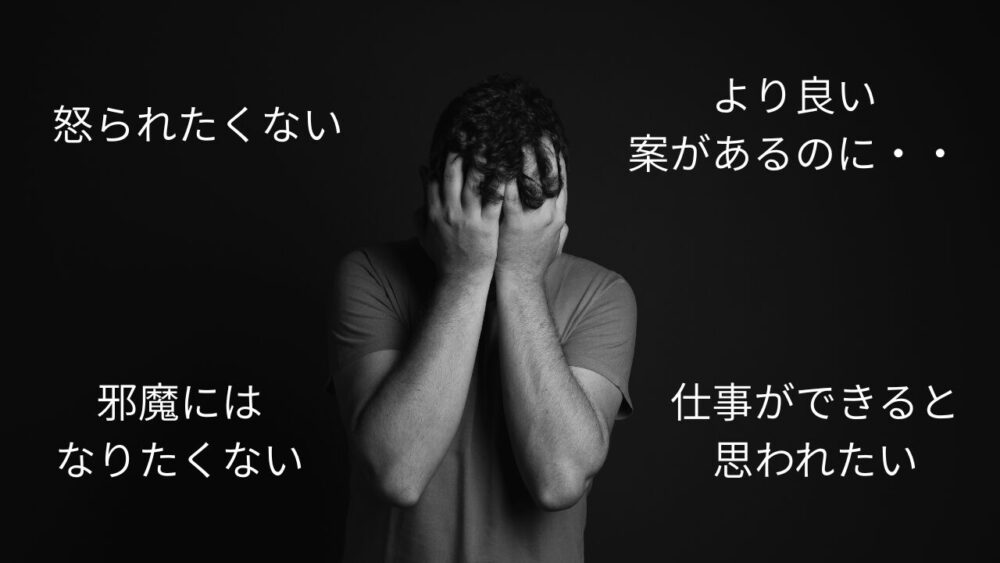
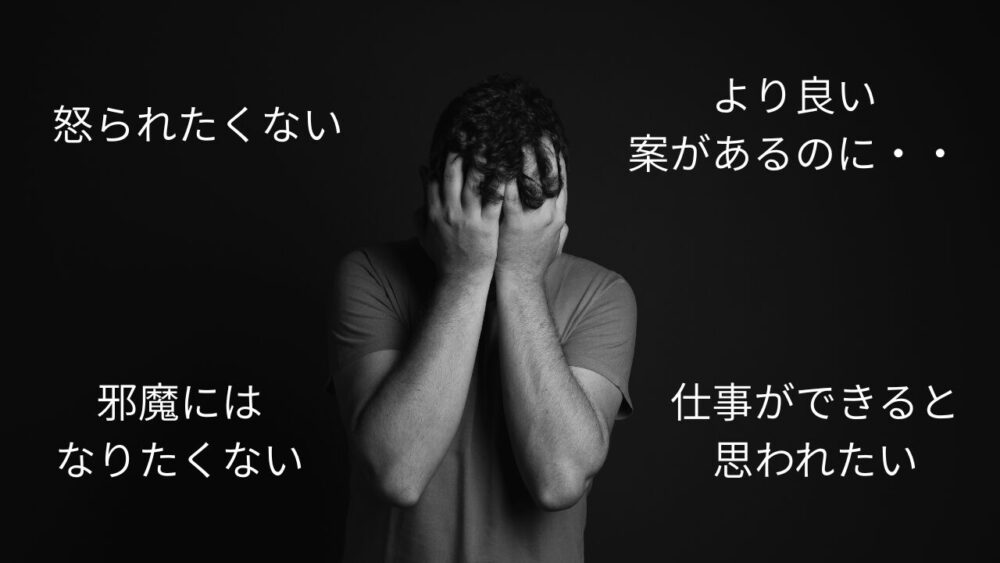
マネージャーのフィードバックは、これらの不安を増幅させもします。
また、取り除くこともできます。
悪循環のサイクル
- 「君は主体性がないね」といった人格を評価する。
- 部下は「無能だ」というレッテルを貼られたと感じる。
- 心理的安全性は低下する。
- 挑戦や発言を恐れるようになる。
- さらに「主体性がない」ように見えてしまう。
好循環のサイクル
- 具体的で行動に焦点を当てたフィードバックをする。
- 「あなたを尊重し、成長を支援したい」という意図を伝える。
- 信頼関係が生まれ、心理的安全性が向上する。
- 部下はフィードバックを前向きに受け入れる。
- 自ら挑戦し、発言するようになる。
どちらも1つのフィードバックから起こる行動です。ただ、フィードバックの方法により効果も影響も全く変わってしまいます。
効果的なフィードバックとは、リーダーの最も重要な行動なのです。
チームの成長の土壌である心理的安全性を耕すフィードバックを身につけましょう!
【実践編】明日から使える!フィードバックの黄金律「SBIモデル」完全マスター
「どう言えば、相手を傷つけずに伝わるだろう?」「自分の主観だと思われずに、客観的に指摘したい…」
この悩みを解決するフレームワークが「SBIモデル」です。
SBIモデルとは?主観を排除する最強のフレームワーク
SBIモデルは、フィードバックを3つの客観的な要素で構成します。
- S (Situation): 状況 – いつ、どこで
- B (Behavior): 行動 – 相手が「何をしたか」
- I (Impact): 影響 – それが「どんな影響を与えたか」


このモデルには最大の強みがあります。
それはフィードバックから主観的な「評価」や「解釈」を完全に排除する点です。客観的な「事実」に基づいて対話を進めます。これにより相手の防御的な反応は劇的に減ります。
SBIの3要素を徹底分解
SBIの3要素は簡単に以下の表のようにまとめられます。
| 要素 | ポイント | OK例 | NG例 |
|---|---|---|---|
| S: 状況 | いつ、どこでの出来事かを具体的に特定する。 | 「今朝11時のチーム定例で、新プロジェクトについて話していた時ですが…」 | 「この前の会議でさ…」 |
| B: 行動 | 相手の具体的な行動や発言を、ビデオカメラのように客観的に描写する。解釈や評価は入れない。 | 「クライアントからの質問に対し、データを3つ提示して説明していましたね。」 | 「素晴らしいプレゼンだったね。」 |
| I: 影響 | その行動が周囲に与えた影響を伝える。「私はこう感じた」というI(アイ)メッセージが基本。 | 「そのおかげで、クライアントの懸念が払拭され、本当に助かりました。」 | 「みんな助かったって言ってたよ。」 |
I(アイ)メッセージで伝えることについては以下の記事でもう少し詳しく記載しています!興味がある方はご一読ください!
【場面別】フィードバック黄金フレーズ集7選(フランクな上司編)
ここではマネージャーが直面しがちな7つの場面を取り上げます。ありがちなNG例と、SBIモデルを活用したOK例を対比形式で紹介します。



明日から即実践してみましょう!
1. ポジティブな貢献を「具体的に」褒めたい時
- やりがちなNG例: 「〇〇さん、いつも積極的で助かるよ。素晴らしいね!」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「この前のA社向けの会議の時なんだけど、」
- B: 「みんなが見落としてた潜在リスクのこと、ズバッと指摘してくれたよね。」
- I: 「あれ、めちゃくちゃ助かったよ。おかげで前もって手を打てたし、提案のクオリティがグッと上がった。あの指摘がなかったら、正直ヤバかったかも。本当にありがとう!」
2. 締切遅れなど「ネガティブな事実」を伝えたい時
- やりがちなNG例: 「また締切に遅れたね。時間管理、ちゃんとしてくれないと困るよ。」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「ちょっといい?先週金曜締め切りだったBプロジェクトの報告書の件なんだけど、」
- B: 「今日の午前中の段階で、まだ提出されてなくて、特に連絡もなかったみたいだね。」
- I: 「これがないと次の作業に進めなくて、チーム全体のスケジュールが押しちゃうのがちょっと心配で。もし何かトラブルとかで困ってるなら、相談に乗るから教えてくれないかな?」
3. 成果物のクオリティ改善を「前向きに」促したい時
- やりがちなNG例: 「この資料、分かりにくいな。もっとちゃんと作ってよ。」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「さっき見させてもらった、クライアント向けの新機能の資料のことなんだけど、」
- B: 「専門用語がちょっと多めで、特に3ページのグラフが、パッと見て何を伝えたいのか分かりにくいかなって感じたんだ。」
- I: 「このままだと、お客さんが『?』ってなっちゃって、せっかくの機能の良さが伝わらないかも。どうしたらもっと分かりやすくなるか、一緒に考えてみない?」
4. 会議で発言しないメンバーに「安心して」発言してほしい時
- やりがちなNG例: 「〇〇さんは、何か意見ないの?もっと発言してよ。」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「さっきのキャッチコピーのブレストの時なんだけど、」
- B: 「何回か、何か言おうとしてやめる感じに見えたんだけど、気のせいかな?」
- I: 「〇〇さんの視点って面白いし、チームにとってすごく良い刺激になるから、何か思ってることがあったらぜひ聞きたいんだよね。もし『ちょっと言いにくいな』って感じだったら、やり方とかも考えたいし、どうかな?」
5. 他者の話を遮るなど「問題行動」を指摘したい時
- やりがちなNG例: 「人の話を遮るのはやめて。失礼だよ。」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「今日のマーケとの会議で、〇〇さんが話してた時なんだけど、」
- B: 「話の途中で、2回くらい割って話し始めちゃってたよね。」
- I: 「それでちょっと話が止まっちゃって、スムーズに進まなかった感じがしたんだ。色んな人の話を最後まで聞いた方が、きっともっと良い結論が出ると思うんだけど、どう思う?」
6. 部下がミスを報告してきた時に「信頼関係」を築きたい時
- やりがちなNG例: 「なんでこんなミスしたんだ!次から気をつけてよ。」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「C案件の見積もりの計算ミスの件、」
- B: 「すぐに報告してくれて、正直に話してくれたね。」
- I: 「まず、教えてくれてありがとう。お客さんに出す前に気づけて、本当に助かった。失敗は誰にでもあるから、隠さずに言ってくれたことが一番嬉しいよ。じゃあ、なんでこうなっちゃったか、次どうするか、一緒に考えようか。」
7. リモートワークでの「報連相」を改善したい時
- やりがちなNG例: 「最近、何やってるか全然見えないんだけど。ちゃんと報告して。」
- 成長を促すOK例 (SBI活用):
- S: 「リモートでやってるDプロジェクトのことで、先週のことなんだけど、」
- B: 「週明けの月曜まで、進捗の共有がなかったよね。」
- I: 「今どうなってるか見えないと、何か手伝えることがあっても気づけないし、ちょっと心配になっちゃうんだ。1日の終わりにチャットで一言『ここまで終わったよ』みたいに共有してくれると、こっちも安心だし、やりやすいんだけど、どうかな?」
フィードバックを「対話」に変える傾聴と問いかけの技術
SBIモデルの型がわかれば、次はフィードバックを真の「対話」にする技術が必要です。
主役は話す側のマネージャーから、聞く側の部下へと移ります。
SBIの次の一手:フィードバックからコーチングへ
SBIで伝えた後が、部下の成長にとって最も重要な時間です。一方的に話して終わってはいけません。
「傾聴」と「問いかけ」が重要です。部下自身の気づきと内省を促すためのポイントを以下に紹介します。
最強のスキル「アクティブリスニング(傾聴)」の基本
傾聴とは、相手が「深く理解してくれている」と感じられる積極的な関わりです。
- オウム返し(パラフレーズ):
「なるほど、つまり〇〇が課題だと感じている、で合っていますか?」と自分の言葉で要約して返す。 - 感情に寄り添う:
「それは大変でしたね」「その状況では、焦るのも無理ないと思います」と言葉の裏にある感情を汲み取る。 - 最後まで聴き切る:
解決策を言いたくなる衝動を抑えましょう。相手が話し終えるのを辛抱強く待つことが大切です。沈黙を恐れないでください。
部下の内省を引き出す「パワフルな問いかけ」の例
「はい/いいえ」で終わる質問は避けましょう。相手に考えさせる「開かれた質問」が重要で、これが対話の質を高めます。
- SBIIモデル(Intent: 意図を尋ねる)SBIで伝えた後に意図を尋ねます。「その行動で何を達成したかったですか?」と聞きましょう。あるいは「どういう意図でそう発言しましたか?」と問いかけます。これにより行動と意図のギャップに本人が気づきます。
- 経験からの学習を促す問い
- 「今回の経験から、一番の学びは何でしたか?」
- 「もし次にもう一度同じ状況になったら、今度はどんな風に取り組みますか?」
- 視点を変え、可能性を広げる問い
- 「もし、予算や時間の制約が全くなかったとしたら、本当はどうしたいですか?」
- 「このプロジェクトで、あなたが『特に大事にしたい』と考えている価値観は何ですか?」
- 行動とサポートを具体化する問い
- 「それを実現するために、まず何から始めますか?」
- 「私から、どのようなサポートがあれば、一番仕事が進めやすくなりますか?」
さらなる成長を目指すリーダーのための推薦図書
本記事で解説した内容をさらに深められるよう、日々の実践に活かすための羅針盤となる書籍を紹介します。
問いかけのスキルを体系的に学びたい
『問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術』(安斎勇樹 著)
チームの状況を「見立て」、効果的な質問を「組み立て」、相手に「投げかける」技術を学べます。1on1や会議の質を劇的に変えたいリーダーにおすすめです!
心理的安全性の理論的背景を深く知りたい
『チームが機能するとはどういうことか』(エイミー・C・エドモンドソン 著)
心理的安全性の提唱者本人による「原典」。なぜ現代において「学習するチーム」が不可欠なのか、その理論と実践的アプローチを深く理解できます。テクニックの「なぜ」を知りたいリーダー必読の書です。
日本の職場で実践するためのヒントが欲しいなら
『心理的安全性のつくりかた』(石井遼介 著)
心理的安全性を日本の組織文化に合わせて、極めて実践的に解説した名著。「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」という4つの因子に基づき、明日から使える具体的な言葉遣いや行動例が満載です。
まとめ:あなたの言葉が、チームを変える。今日から始める第一歩
本記事では、フィードバックの技術についてその核心を解説してきました。部下と自分自身の成長を加速させるための技術です。
最後に、最も重要なポイントを振り返ります!
- 心理的安全性は、成長が生まれる土壌である。 恐れのない環境こそが、率直な対話と挑戦を可能にする。
- SBIモデルは客観的で明確なフィードバックの道具である。 主観を排し事実に基づいて伝えよう。そうすることで信頼を築ける。
- 傾聴とパワフルな問いかけが、フィードバックを真の「対話」に変える。 一方的な指示ではなく、共創の場をつくりだす。
大切なのは、完璧を目指さず最初の一歩を踏み出すことです。次の1on1で、この記事の「黄金フレーズ集」を使ってみてください。
会議で良い発言があったら、SBIモデルで具体的に褒めてみる。部下がミスを報告してきたら、「報告してくれてありがとう」と感謝から始めてみる。
その小さな行動の変化が、部下との関係性を変えます。
成長志向のリーダーへの旅は、たった一つの対話から始まります。
今日から始めてみましょう!
もっと部下と上司の関係性を深めたい方はこちらの記事もご一読ください!

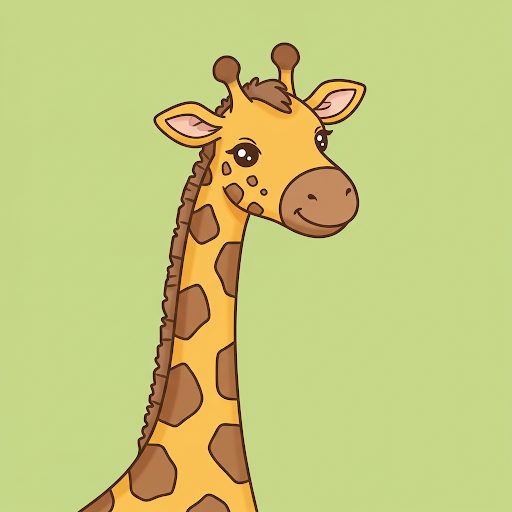
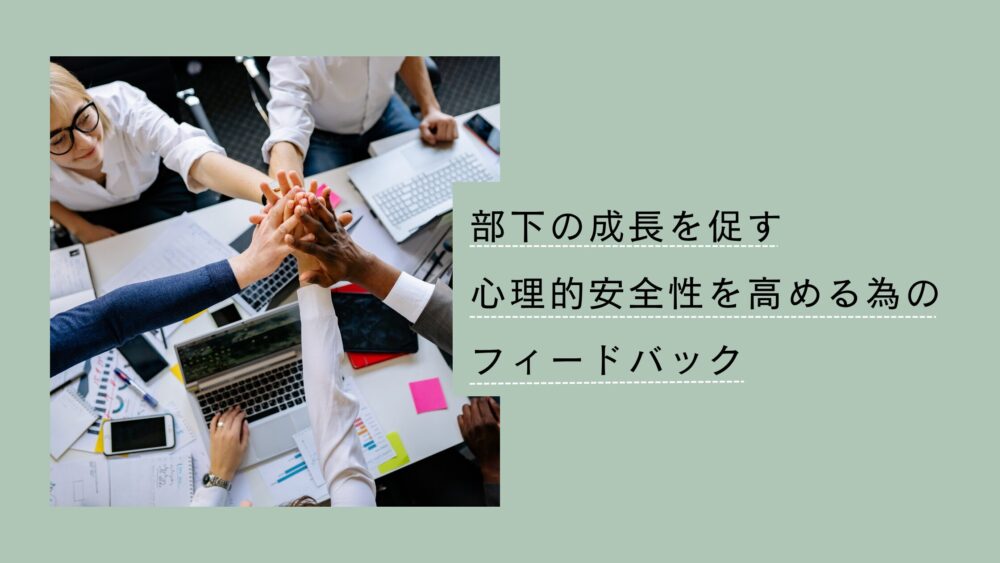




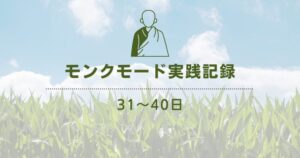

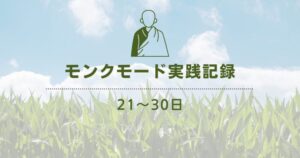
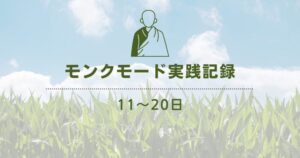
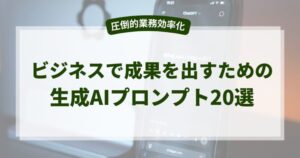
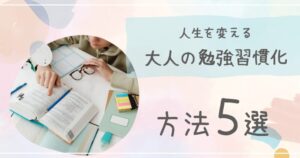
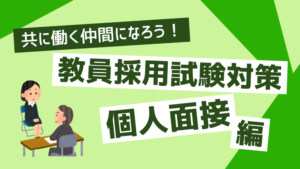
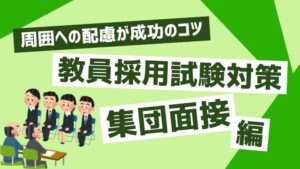
コメント